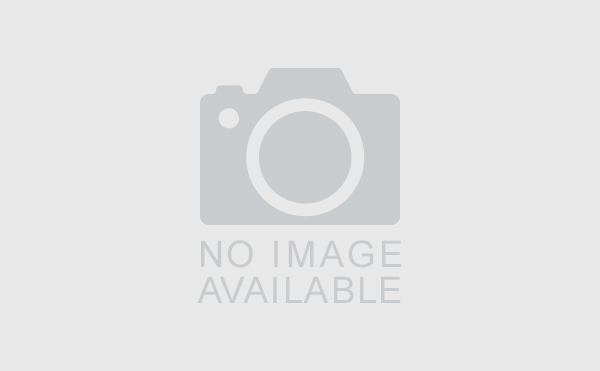主の祈り
2017年5月21日復活節第6主日礼拝説教より(竹澤知代志主任牧師)
「見てもらおうとして、人の前で善行をしないように注意しなさい。さもないと、あなたがたの天の父のもとで報いをいただけないことになる。だから、あなたは施しをするときには、偽善者たちが人からほめられようと会堂や街角でするように、自分の前でラッパを吹き鳴らしてはならない。はっきりあなたがたに言っておく。彼らは既に報いを受けている。施しをするときは、右の手のすることを左の手に知らせてはならない。あなたの施しを人目につかせないためである。そうすれば、隠れたことを見ておられる父が、あなたに報いてくださる。」
「祈るときにも、あなたがたは偽善者のようであってはならない。偽善者たちは、人に見てもらおうと、会堂や大通りの角に立って祈りたがる。はっきり言っておく。彼らは既に報いを受けている。だから、あなたが祈るときは、奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば、隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。また、あなたがたが祈るときは、異邦人のようにくどくどと述べてはならない。異邦人は、言葉数が多ければ、聞き入れられると思い込んでいる。彼らのまねをしてはならない。あなたがたの父は、願う前から、あなたがたに必要なものをご存じなのだ。だから、こう祈りなさい。
『天におられるわたしたちの父よ、
御名が崇められますように。
御国が来ますように。御心が行われますように、
天におけるように地の上にも。
わたしたちに必要な糧を今日与えてください。
わたしたちの負い目を赦してください、
わたしたちも自分に負い目のある人を
赦しましたように。
わたしたちを誘惑に遭わせず、
悪い者から救ってください。』
もし人の過ちを赦すなら、あなたがたの天の父もあなたがたの過ちをお赦しになる。しかし、もし人を赦さないなら、あなたがたの父もあなたがたの過ちをお赦しにならない。」マタイによる福音書 6章1〜15節
▼2節と5節とで3回も出て来る偽善者という言葉の語源は、舞台の上に立って演技する者、俳優です。ギリシャの古典劇で、演技者は役柄に合わせて、仮面・ペルソナを被って舞台に立ちます。舞台の上では、自分の素顔・正体を隠すことから、偽善者という意味になりました。偽善者、そこに素顔、真実はありません。素顔を隠している、素顔がなくなっているということが、既に偽善なのです。
▼素顔のままでは絶対に出来ないような、悪事をも、仮面を付け替えると出来てしまう、当たり前のように行ってしまうのです。何よりも、兵士の仮面であり、役人の仮面です。会社員という仮面をつければ、賄賂を送ったり、裏金を作ったり、いかがわしい接待をしたり、そういう悪事が出来てしまうのです。悪事をしているのは、本当の自分ではなく、仮面です。そういうことで、納得してしまうのです。自分で免罪しているのです。
▼トルストイの『復活』にこんな場面があります。シベリアに連行されていく囚人たちに、兵士たちは辛く当たります。まるで家畜のように扱い、思いやり・労りのかけらもありません。その様子を見て、主人公のネフリュードフ公爵は思います。生まれ育ちもあまり変わらない囚人に対して、兵士たちひとり一人は、同情心を持っている。しかし、兵士たちは兵士という仮面を付け、囚人には囚人という仮面を被せ、その結果は、こんなにもむごたらしい真似が平気で出来る。
▼実はネフリュードフも仮面を被っています。若い時には放蕩な貴族の仮面、深く人生を悔い改めた今は、信仰者、慈善家としての仮面、しかしそれは仮面でしかありません。
ネフリュードフは自分が若い時に深く傷つけ、ために娼婦に身を落とし、今は囚人として護送され行くカチューシャのために罪を贖おうと努力し、彼女との結婚を決意します。
これに対して、カチューシャは心開くことをしません。彼女はネフリュードフに言います。「あんたは、私をだしにして救われたいと願っているのだろう」。
しかし、これは彼女の本心ではありません。彼女はその心の奥深くに、少女の純真とネフリュードフへの愛を持っています。しかし、娼婦・囚人の仮面の陰にそれを隠しているのです。
『復活』という大作を数行で論じることはできませんから、もう止めにしますが、『復活』とは、神さまの前に立つ人間の仮面と素顔の物語でもあります。
▼今日の箇所で述べられている偽善者は、1節、『見てもらおうとして、人の前で善行をし』5節、『人に見てもらおうと、会堂や大通りの角に立って祈りたがる』とあります。
その結果、3節『彼らは既に報いを受けている』、5節『彼らは既に報いを受けている』とあります。普通に考えれば、何しろ偽善者のことですから、見栄え良くやっているようだけれども、実は内実は火の車だとか、肉体は死の病に捕らえられているというような意味かと思います。
▼しかしここで使われている報いというギリシャ語は、ミソスです。今日の言葉なら、ボーナスです。彼らは役者だから、その報いを、出演料=ギャラとして受け取ってしまっています。だから、天国の門での裁きの時に、それ以上の報酬・ギャラはありません。もう勘定は終わっているのだから、天国で受け取る分は何も残っていません。こういう意味です。
▼ここに登場する偽善者とは、ファリサイ・律法学者です。その背景を簡単にお話します。今日で言えば私塾ということになりますでしょうか。学校です。ここに描かれているように、辻に立って、演説したりお祈りしたりすると、それが弟子の勧誘になります。
要するに、2節、『人からほめられようと会堂や街角で』演説するのです。それが弟子の勧誘になります。その結果は、『人からほめられ』、弟子が集まります。
初めから、神さまに向けて祈っているのではありませんから、当然、この祈りは、神さまの所には届かないでしょう。
▼そこで、神さまの所に届くように祈りたかったなら、6節、
『あなたが祈るときは、奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば、隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる』。
真に、祈りたいと思うならば、隠れた所で、人々からの賞賛という報いを得ないようにして、祈らなくてはならないのです。『施し』についても同様です。
▼まるで、神さまは聞いていないかのように、祈ることがあります。神さまに近況報告をすることがあります。状況説明することがあります。しかし、神さまが人間に教えて貰わなければならないことは何もありません。情報でも、教えでも、そして、その人の心の内側のことでも。
▼イエスさまが、私たちに主の祈りを下さったのは、私たちの中に、このように、祈りから離れてしまう傾向が強くあるからだと思います。祈りから離れてしまう、祈らなくなるということではありません。偽善者の祈りに走ってしまうのです。
▼宗教改革の意味、礼拝改革とか教会政治の改革とかいろんな意味が重なっていると思いますが、何と言っても、最大のことは、誰もが自分の国の言葉で聖書を読むことが出来るようになったという点です。そしてもう一つの宗教改革の意味、誰もが自分の言葉で祈ることが出来るようになったことです。
▼偽善者の祈りは、全くこの逆の仕業です。人々の賞賛を目的としてなされる偽善者の祈りは、結局は、祈りを独占しているのです。人々の賞賛を目的としてなされる偽善者の祈りは、その祈りを聞いている者をさえ、阻害しているのです。
偽善者の祈りに必要なのは、自分自身だけです。神さまも、人も、本当は要らないのです。
▼1節から改めて読みます。
『「見てもらおうとして、人の前で善行をしないように注意しなさい。
さもないと、あなたがたの天の父のもとで報いをいただけないことになる』。
『見てもらおうとして、人の前で善行を』する人は、神さまが見ていることを信じていない人です。『天の父のもとで報いをいただけ』るとは思っていない人です。
もっと簡単に言えば、信仰のない人です。
▼2節前半。
『だから、あなたは施しをするときには、
偽善者たちが人からほめられようと会堂や街角でするように、
自分の前でラッパを吹き鳴らしてはならない』。
こんな人が実際にいます。自己顕示欲が強いのでしょうか。自己顕示欲が強いだけなら、これはあくまでも性格のことであって、特に咎め立てする必要はないかも知れません。
問題は、『施し』も『お祈り』も、自分の業、自分の手柄としていることです。
▼こなん機会にしか言えません。この箇所を読む時にしか言えません。かなり耳障りが悪いかも知れませんが、敢えて申します。あと10数回しかこの講壇に立てない牧師としては、話す責任があると考えるからです。
赴任して間もなくの頃、祈祷会に集まる人は、夜はほぼゼロ、昼は年配のご婦人ばかりでした。年配の方の祈りは、どうしても長くなります。短い言葉では表せない、それだけの思いがあるのだから、それもよろしいでしょう。
これに対して若い人から、何時終わるとも分からない長い祈りを聞くのは辛い、何時に帰れるか分からないのでは、祈祷会に出席出来ないと指摘がありました。これももっともな意見ですが、私は牧師であっても、人様の祈りについてとかく批評するのは憚られると考えて、何も言いませんでした。
▼結果、前半の聖書研究は讃美歌も含めて30分未満なのに、後半の祈祷会は1時間近くになりました。そして、そこに新しい年配の出席者が加わりました。この人の祈りがまた長い、15分20分、とうとう25分一人で祈り続けました。この時は、時計を見てはかってしまいました。
祈りの内容面にもかなり問題があったのですが、つまり、祈りの中で牧師批判をするとか、そのことには触れません。兎に角長過ぎます。30分どころか60分祈っても足りない時もありますでしょう。涙を流しながら祈る時もありますでしょう。絶叫する時だってあるかも知れません。真剣な祈りだからこそ。
しかし毎回毎回、20分も祈るのはどうでしょう。結果的には、祈祷会の破壊になってしまいます。
そこで、個人への攻撃にならないように言いました。あまり時間が長いと出席出来ない方もあります。祈りについて、長いの短いのと言うことは本来憚られますが、祈祷会を守り、一人でも多くの方に出席頂けるように、少し短めにお祈り下さい。
▼何人かの人が、自分の祈りが長過ぎたと指摘されたと受け止め、傷付いてしまったようです。
一番肝心な人は、ますます長く、ますます説教批判をし、終いには、牧師がちゃんと祈れますようにと祈りました。
そしてやがて出席しなくなりました。
耳障りの悪い話でした。しかし、自分を主張するあまり、集会を破壊してしまうのは、矢張り許されないことでしょう。
▼2節後半。
『はっきりあなたがたに言っておく。彼らは既に報いを受けている』。
人間のやることですから、慈善にも祈りにも、出来不出来があるかも知れません。しかし、それが肝心なことではありません。肝心なことは、神さまに向かって祈っているのかどうかだけです。神さまに向けられたものでなければ、どんなに麗々しい言葉を連ねても、本当は祈りではありません。
▼3節。
『施しをするときは、右の手のすることを左の手に知らせてはならない』。
非常に文学的神学的な表現ですが、簡単に言えば、自己陶酔であってはならない、偽善であってはならないということでしょう。
偽善的な祈りの結果『既に報いを受けている』偽善者は勿論ですが、例えば、施しをして気分が良かったと思った瞬間に、『既に報いを受けている』のです。
▼4節。
『あなたの施しを人目につかせないためである。
そうすれば、隠れたことを見ておられる父が、あなたに報いてくださる』。
方便的な表現です。要は、兎に角神さまに向かい合いなさい、人の目の前に立つことを目的としてはならないということでしょう。
もっと簡単に言えば、神さまが祈りを聞いて下さると信じて祈りなさい、神さまがいると信じて祈りなさいということでしょう。
▼5節は先に読みました。6節。
『だから、あなたが祈るときは、奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、
隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば、
隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる』。
これが私たちに与えられている祈りの形です。重大なことです。イエスさまの直接のお言葉なのですから。
そして、この言葉をも含めて、この6章、これ程、無視され、ないがしろにされているイエスさまのお言葉は、他にありません。
▼勿論、この教えを徹底していたら、祈祷会などは成立しません。礼拝も困難です。それに、新約聖書中にも、ペトロやパウロ、その他の弟子たちの祈りが、収録されています。イエスさまの祈りもあります。これらは、人前での祈りだからこそ、収録されています。
しかし、6節を無視してはなりません。人の前で祈る必要があるときでも、この6節の教えを大前提とすべきでしょう。
少なくとも、劇中の台詞のような、聴衆を強く意識した祈りは無用と考えます。
自己弁明に聞こえるかも知れませんが、あの牧師の祈りは力強いとか、まして上手だとか、逆に下手だとかと批評することは、教会の中の悪習だと、私は思います。
礼拝の司会者も、献金の祈りも、このようなことは退けなければなりません。
▼徹底して聖書に忠実な教会というものがあります。このような教会は大抵、肝心な所で聖書の根本思想から外れていて、異端的なのですが。自称聖書に忠実な教会でも、公然の祈りはしないという教会はありません。6章に厳密なら、そんな教会があっても不思議ではないと思います。
逆に、公の祈りは全て成文化されていて、信徒が自分の言葉で祈ることはしない教会があります。これは、決して少なくありません。むしろ、多数派でしょう。プロテスタント以外は原則そうですし、プロテスタントの中でも少なくありません。長老主義のような改革派の教会でも珍しくはありません。
▼宗教改革の意味、礼拝改革とか教会政治の改革とかいろんな意味が重なっていると思いますが、何と言っても、最大のことは、誰もが自分の国の言葉で聖書を読むことが出来るようになったという点です。
ヒエロニムスのラテン語聖書が、公式のローマカトリックの聖典です。他のものは、その翻訳でしかありません。つまり、ラテン語聖書は、ローマカトリックの独占物だったのです。
ミサもラテン語です。ミサの語源は秘密=神秘だと言うことは、周知のことです。
宗教改革の結果、誰もが自分の言葉で礼拝に与り、自分の言葉で、聖書を聞くことが出来るようになったのです。
だからこそ、私たちプロテスタントの信仰者は、このことを大事にしなければなりません。自分の言葉で歌い、自分の言葉で祈ることが許されているのですから。それを自ら損なうようなことをしてはならないのです。
▼7節。
『また、あなたがたが祈るときは、異邦人のようにくどくどと述べてはならない。
異邦人は、言葉数が多ければ、聞き入れられると思い込んでいる』。
これは注釈するまでもないでしょう。
8節。
『彼らのまねをしてはならない。あなたがたの父は、願う前から、
あなたがたに必要なものをご存じなのだ』。
神さまへの信頼、これが祈りの大前提です。
▼主の祈りが与えられたことの意味は、この点にこそあります。主の祈りの内容も勿論重要です。しかし、内容と共に大事なことは、私たちが祈ることの出来る言葉が与えられたということです。祈ることが許されたのです。言葉が与えられたのです。