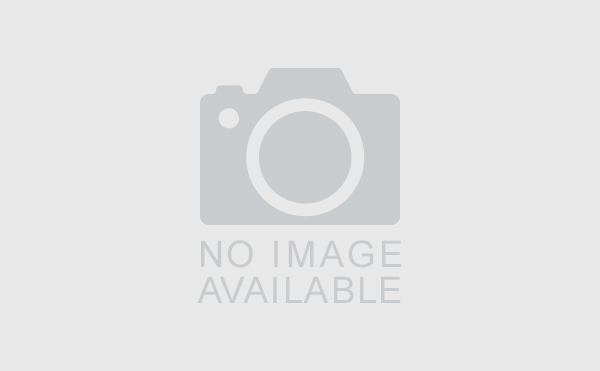道なり真理なり命なり
2017年5月14日復活節第5主日礼拝説教より(竹澤知代志主任牧師)
「心を騒がせるな。神を信じなさい。そして、わたしをも信じなさい。わたしの父の家には住む所がたくさんある。もしなければ、あなたがたのために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなたがたのために場所を用意したら、戻って来て、あなたがたをわたしのもとに迎える。こうして、わたしのいる所に、あなたがたもいることになる。わたしがどこへ行くのか、その道をあなたがたは知っている。」トマスが言った。「主よ、どこへ行かれるのか、わたしたちには分かりません。どうして、その道を知ることができるでしょうか。」イエスは言われた。「わたしは道であり、真理であり、命である。わたしを通らなければ、だれも父のもとに行くことができない。あなたがたがわたしを知っているなら、わたしの父をも知ることになる。今から、あなたがたは父を知る。いや、既に父を見ている。」フィリポが「主よ、わたしたちに御父をお示しください。そうすれば満足できます」と言うと、イエスは言われた。「フィリポ、こんなに長い間一緒にいるのに、わたしが分かっていないのか。わたしを見た者は、父を見たのだ。なぜ、『わたしたちに御父をお示しください』と言うのか。わたしが父の内におり、父がわたしの内におられることを、信じないのか。わたしがあなたがたに言う言葉は、自分から話しているのではない。わたしの内におられる父が、その業を行っておられるのである。わたしが父の内におり、父がわたしの内におられると、わたしが言うのを信じなさい。もしそれを信じないなら、業そのものによって信じなさい。
ヨハネによる福音書 14章1〜11節
▼先ずは、6節。
『わたしは道であり、真理であり、命である』。
『わたしは道であり』の『道』には、ギリシャ語でホドスという字が当てられています。もともとは人間が歩く道のことを指していますが、次第に、人生の道、信仰の道というように、特別の意味が込められて来ます。このことは、多くの宗教・思想に共通していると言っても良いでしょう。元来はペルシャあたりの宗教に起源を持つものと聞きました。
信仰を、信仰道だと言う人がいます。その通りかも知れません。歩き続け究めるのが信仰道でしょう。
▼この『道』が、キリスト教に於いて、他の宗教以上に特別の強調を以て語られるのには、理由があります。申命記26章5節の最も古い形の信仰告白が『私の先祖はさすらいの一アラム人でありましたが…』と言い表すように、父祖アブラハム・イサク・ヤコブ即ちイスラエルの物語から、出エジプト記の出来事の全体、更にはバビロン捕囚からの帰還の旅というふうに、旧約聖書・イスラエルの歴史は旅の連続です。
つまり、ユダヤの人にとって『道』を人生に準えることは、決して観念的なことではなく、ごく実際的なことだった訳です。
▼そして、何よりも、新約聖書の時代に入っても、イエスさまの公生涯は、これ全て旅でした。十字架の出来事の後も、使徒たち特にペトロ・パウロの伝道の旅行が続来る。
▼ところで、『道』これは、文字通りの道路の事ですが、主要な都市を結ぶ道路が整備・舗装され、宿場が整えられたのは「全ての道はローマに続く」と言われたように、ローマ帝国が誕生してからのことです。イスラエルでも、ローマ支配の時代になって飛躍的に整備されたと言われます。
▼アブラハムやイサク・ヤコブの時代には、そのようなものはありません。それはモーセでも同じです。アブラハムやイサク・ヤコブつまり、小さい家畜を飼い、時に小規模の貿易を生業とするユダヤ人のご先祖は、砂漠や荒野の中を歩き、テントに寝泊まりしました。むしろ、彼らの頻繁に歩いた所が道になって来るし、井戸が掘られ、町が出来て来る。
▼ユダヤの人たちが、そのご先祖の踏み固めた道を歩くように、私たちもまた、私たちの信仰の先達の歩いた足跡を辿りながら、信仰の歩みなしています。私たちにとっては、この道を外れ見失うことが、即ち信仰の道を踏み外すこととさえ思われます。
▼私たちの教会に連なる方が召されるということは、こんなふうに譬えることができるかも知れません。同じ道を歩いているのだけれども、先頭を行く者の、姿が後ろの者には見えなくなった。それはいかにも、後続の者には頼りない気持ちが致します。しかし、もし他にこの道を歩いているものがいなかったなら、後の者は迷子になるかも知れませんが、少し先を進むものやら、遅れて来るものやらがいるから、決して迷子になることはありません。
同じ信仰の道を一緒に歩く者が、あまり寂しいのも困りますが、一方道が太くて往来が激しいとどうでしょうか、旅人は寂しい思いをしなくて住むかも知れませんが、逆に反対方向に進む者やら、横断する者やらがいますし、自分の行き先を見失うことにつながるかも知れません。一方通行の狭い道のようだけれども、私たちの教会の歩く道は決して間違っていないと考えます。
▼サテ、今まで申し上げましたのは、いわば、葬儀用の話、つまり、教会員以外の方も大勢おられる場面を想定したものです。
私はあくまでも、信仰の道の話をしているのですが、葬儀の列席者即ち聴衆が、それを何々家の歩んで来た道に重ねて、受け止めていただいても、かまわないのです。
しかし、この後でお話しすることは、信仰以外のものには多分重ならないだろうと思います。
▼順に読みます。
1節。これは、明らかに、前の章に出て来る受難予告との関連で、語られています。イエスさまは、ご自分が十字架に架けられて殺されるという、何ともショッキングな預言をなさいました。このことは、全ての弟子たちにとって、あまりにも意外で、とても理解出来ないものでした。この受難予告に対して、二通りの反応が生まれます。一つは、ペトロのものです。彼は、あまりにも意外で、あまりにも辛い預言だったからこそ、とことんまで、イエスさまに従うことを決心致します。悲愴な覚悟をしたのです。
一方、イスカリオテのユダ、彼はこの時から、イエスさまに従うことを躊躇し、疑問を覚えるようになります。正反対の反応です。しかし、動機は別でも、結局、二人ともイエスさまを裏切ることになります。
▼全く正反対の反応に見えながら、実は、この二人の反応には、共通点があります。つまり、イエスさまの預言に、冷静に対応することが出来ません。どのように対応すべきかを、イエスさまに問うことが出来ません。
冷静に対応し、冷静に問うたのは、トマスです。このトマスこそ、同じヨハネによる福音書の20章25節で、『あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、また、この手をそのわき腹に入れてみなければ、わたしは決して信じない』と言った人です。
心を騒がせないこと、これが大事です。
▼しかし、トマスは、先程の一件では、容易に信じなかったために、『わたしを見たから信じたのか。見ないのに信じる人は、幸いである』と言われています。
神を信じること、これが大事です。人生の重大事に対しては、こうでなくてはなりません。
往々にして、心を騒がせ、そして信じないのが、私たちの現実です。心を騒がせないで、じっと見ていて、じっと聞いていて、そして信ずる、なかなか出来ません。
▼2節。
『わたしの父の家には住む所がたくさんある。もしなければ、
あなたがたのために場所を用意しに行くと言ったであろうか』。
『場所』とは、天国のことです。つまり、信仰道を歩き続け辿り着く場所です。それは、使徒たちの時代には殉教の道を意味します。殉教は信仰を貫いた結果です。
▼3節。
『行ってあなたがたのために場所を用意したら、戻って来て、
あなたがたをわたしのもとに迎える。こうして、わたしのいる所に、
あなたがたもいることになる』。
これも殉教のことが強く意識されています。『あなたがたのために場所を用意したら』とは。明らかに十字架のことです。イエスさまが十字架の死を迎えられたのは、『あなたがたのために場所を用意』すること、つまりは私たちの罪を贖い、神の国に入れられる資格を与えることです。
▼『戻って来て、あなたがたをわたしのもとに迎える』。再臨のキリストが予告されています。『こうして、わたしのいる所に、あなたがたもいることになる』。神の国での命が約束されています。
▼4節。
『わたしがどこへ行くのか、その道をあなたがたは知っている』。
ここでは13章の出来事が背景にあります。
13章には、所謂洗足の出来事が描かれています。イエスさまが弟子たちの足を洗い、その上で、十字架の死が予告され、更に、ユダの裏切り、ペトロの離反が預言されます。
『わたしがどこへ行くのか、その道をあなたがたは知っている』とは、十字架の死の予告であり、弟子たちの躓きの予告です。
▼5節。
『主よ、どこへ行かれるのか、わたしたちには分かりません。
『わたしがどこへ行くのか、その道をあなたがたは知っている』とイエスさまが仰るのに、トマスは『どうして、その道を知ることができるでしょうか』と反論します。これは要するに、イエスさまの十字架のことが理解できていないということです。
そして単に知識のことだけではありません。十字架の道を歩む用意が出来ていないということになります。
▼6節が決定的に重要です。
『わたしは道であり、真理であり、命である。
わたしを通らなければ、だれも父のもとに行くことができない』。
富士山に登るには、多様な道、登山道があると言われます。辿り着く目的地が同じならば、どの道を通っても良いではないかという理屈で、価値観や宗教の多様性を説く表現です。富士登山はそうかも知れませんが、信仰を貫く道は、主の十字架の道しかありません。
▼7節。
『あなたがたがわたしを知っているなら、わたしの父をも知ることになる。今から、あなたがたは父を知る。いや、既に父を見ている』。
不思議な論理展開です。『わたしを知っているなら』、イエスさまを知っているなら、それは『父をも知ることになる』、つまり、イエスさまを知ることは父なる神を知ることと結局は、一つことであるという理屈です。つまりは、父なる神は子なる神と同一だということです。
更に『今から、あなたがたは父を知る』、今後やがて『父を知る』ことは、その確実さの故に『既に父を見ている』ことと同じことだといわれています。
つまり、7節が言うのは、父とことは同一だということです。
このことは、初代教会の大論争であったキリスト論、更に三位一体論を考える上で、決定的に重要な資料、証拠だと考えます。
▼ピリポも質問します。8節。
『主よ、わたしたちに御父をお示しください。そうすれば満足できます』。
この理屈は、6・7節と全く同じ理屈です。イエス・キリストに出会いその言葉に触れながら、なお信仰の確信を得られないから、ピリポの発言になります。これはまた、現代でも多くの信仰者の発言です。疑念です。
しかし、イエス・キリストに出会いその言葉に触れながら、なお信仰の確信を得られないなら、他の何によって得られるというのでしょうか。
その故に十字架の出来事が起こらなければならなかったのです。
▼9節。
『フィリポ、こんなに長い間一緒にいるのに、
わたしが分かっていないのか。わたしを見た者は、父を見たのだ。
なぜ、『わたしたちに御父をお示しください』と言うのか』。
これは、トマスとの問答と全く同じ内容を持っています。結論も同じです。『わたしを見た者は、父を見たのだ』。イエスさまと父なる神さまとは同一なのです。
▼『こんなに長い間一緒にいるのに、わたしが分かっていないのか』とのお言葉は、そのまま、現代の私たちにも向けられています。
『こんなに長い間』、これが決定的に重要です。実績、イエスさまと一緒に道を歩いて来た実績が大事なのです。
ここで話はもとに戻ります。『わたしは道であり、真理であり、命である。わたしを通らなければ、だれも父のもとに行くことができない』、この道を歩き続けるしかありません。
▼10~11節も同じ理屈の繰り返しです。
▼弟子たちはひとり一人に若干の違いはあるかも知れませんが、多分三年もの間一緒にいました。イエスさまの言葉を聞き、その業に触れました。
私たちも同様です。信仰道を歩き続けて来たのです。その旅の中にこそ、確信があります。確信を得たいならば、歩き続けるしかありません。